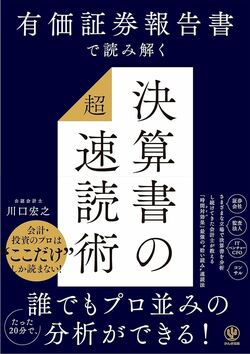流動資産の中身は「1年以内の現金化」を軸に見る
〈ポイント3〉さらに細かく貸借対照表の中身を見る
流動比率の意味が理解できたところで、さらに細かく会社の安全性について考えてみましょう。
ここでは流動資産、流動負債、純資産という3つの項目について、さらに細かく見ていきたいと思います。
・流動資産
流動資産は「1年以内に現金化されるもの」であり、資産の合計額に占める流動資産の比率が高いほうが、会社の安全性が高いと考えられます。
ただ、注意しなければならない点があります。それは、流動資産のなかにも1年以内の現金化が確実なものと不確実なものがあるということです。
流動資産の内訳を見ると、さまざまな項目(勘定科目と言います)が含まれています。どのような勘定科目で構成されているのかは会社によって異なるのですが、一般的には「現金」「預金」「有価証券」「売掛金」、商品や製品などの「棚卸資産」「貸倒引当金」などが含まれています。
このうち、最も確実に現金化できるのは、もちろん金庫の中に入っている現金です。他にも預金はいつでも銀行から引き出せますし、会社が余裕資金を運用するために保有している株式や債券などの有価証券も、証券会社に売却注文を出せば注文が約定された日から起算して3営業日目には現金化されます。つまり現金、預金、有価証券については、1年以内の現金化は確実です。
「売掛金」「棚卸資産」は少ないほうがいい
では、それ以外の流動資産はどうでしょうか。
まず売掛金ですが、これは商品やサービスを顧客に販売したものの、その代金が未回収になっているものを指します。基本的に、支払い期日が到来すれば、その代金は入金されてくるはずですが、不幸にして取引先が倒産してしまったりすると、その代金を回収できる可能性は大きく低下します。
次に、棚卸資産はどうでしょうか。棚卸資産とは、仕入先から購入した商品や、製造した製品が主であり、それ以外にも製造途中の製品である仕掛品、製品のもとになる原材料も含まれます。
これら棚卸資産も、特に何もなければ一定期間後には顧客に販売することができるので、現金化できるわけですが、問題は売れ残りのリスクがあることです。原材料も大量に仕入れ過ぎてしまったら、使い切ることができずに廃棄処分せざるを得ません。
したがって棚卸資産は流動資産に含まれるとはいえ、そのすべてを現金化できるかというと、実はそうではないのです。基本的に、流動資産のなかでも売掛金や棚卸資産は少ないほうがいいと言えます。